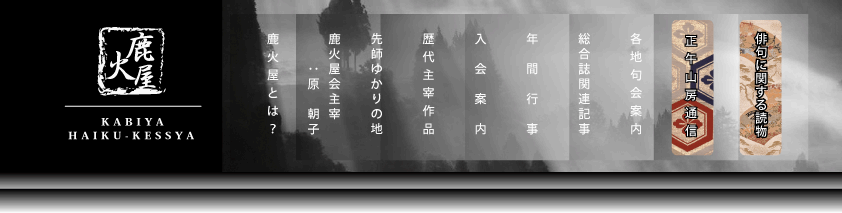
◆正午山房通信
「正午山房」は俳人原石鼎の終の栖で、鹿火屋代々の主宰が住みなしたところ。
原裕が午年の正午の生まれであったことから名づけられました。
四季と向き合う俳句のひとこまをお届けします。
晩秋になると中庭の白山茶花の蕾が目立ち始め、十一月ともなれば白い花を咲かせ始めます。
先駆けの花が開くと、堰を切ったように後から後から花が開いていきます。
それは咲き継ぐというよりは、湧いてくるといった方がいいかもしれません。
山茶花の花期は長く、十二月二十日の石鼎忌にも盛んに花を散らしては咲かせるので、
私の中では山茶花は石鼎忌の花となっています。
石鼎は亡くなるとき、「おかか、おかか」と冥土にいる出雲の母を呼び続けたといいます。
私は盛んに散る山茶花の中で石鼎が命終を迎えたものとばかり思い込んでいましたが、
原裕(当時の堀込昇)の書いた「終焉記」には、常より早く咲き始めた紅梅のはなしが出てきますが、
山茶花のことは書かれていません。
中庭の山茶花がいつ植えられたのかはっきりしませんが、少なくとも石鼎忌が近いことを知らせてくれます。
先日、石鼎忌に先立ち山墓の掃除をしてきましたが、
墓のほとりに植えられた白山茶花が盛りとなり、見事な咲き振りをみせていました。
自然界の移り行きは気まぐれなように見えてもどこかに「約束」があるように思います。
石鼎忌にこんこんと湧くように白い花を咲かせる山茶花もそのひとつといえるでしょう。
白い花が白く咲くのは当たり前のことのように思えますが、それは季節の約束であり、
その姿を見ることによって、私たちは励まされたり、慰められたりするのではないでしょうか。
石鼎忌を教えてくれる花に石蕗の花もあります。
地軸より咲きし色なり石蕗の花 石鼎
は、この地で詠まれた句ですが、地軸を思わせる花は黄泉の国からの石鼎のメッセージのような気もします。
そこで、今年は石蕗の花を活けて供えてみました。
石鼎が亡くなったのは、冬暖かな日の夕方であったと聞きます。
石鼎は、華やかな句柄から春夏の俳人とも呼ばれました。
今年は、生憎、雨となりましたが、冬の最中であっても不思議と春を思わせるような暖かな日和に恵まれることが多いようです。
そして、石鼎忌の翌日か翌々日には冬至が来ます。
冬至は一年の中で夜が最も長い日ですが、日没が最も早い日ではありません。
日没が最も早くなるのは、十二月初旬で、冬至のときには僅か数分ですが、日が長くなります。
これは地球の地軸の傾きや公転軌道が真円形でないことなどが理由に挙げられています。
自然界にはもともとこうしたゆとりやあそびが存在します。
自然界から句種を貰う俳句もまた自然界に倣い、ゆとりを持つ方が大らかに楽しめるのではないでしょうか。
原 朝子
(25・12・21)
|
Copyright (C) 2015 KABIYA Haiku-kessya. All Rights Reserved. |